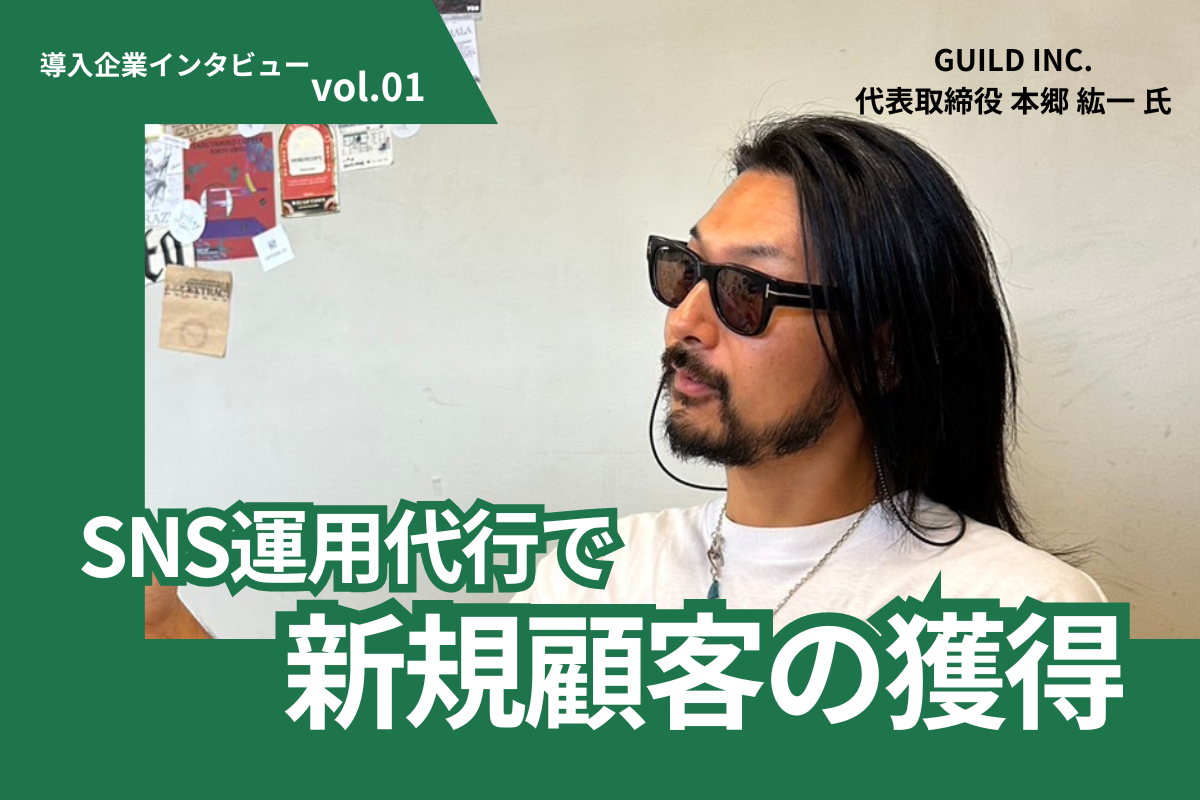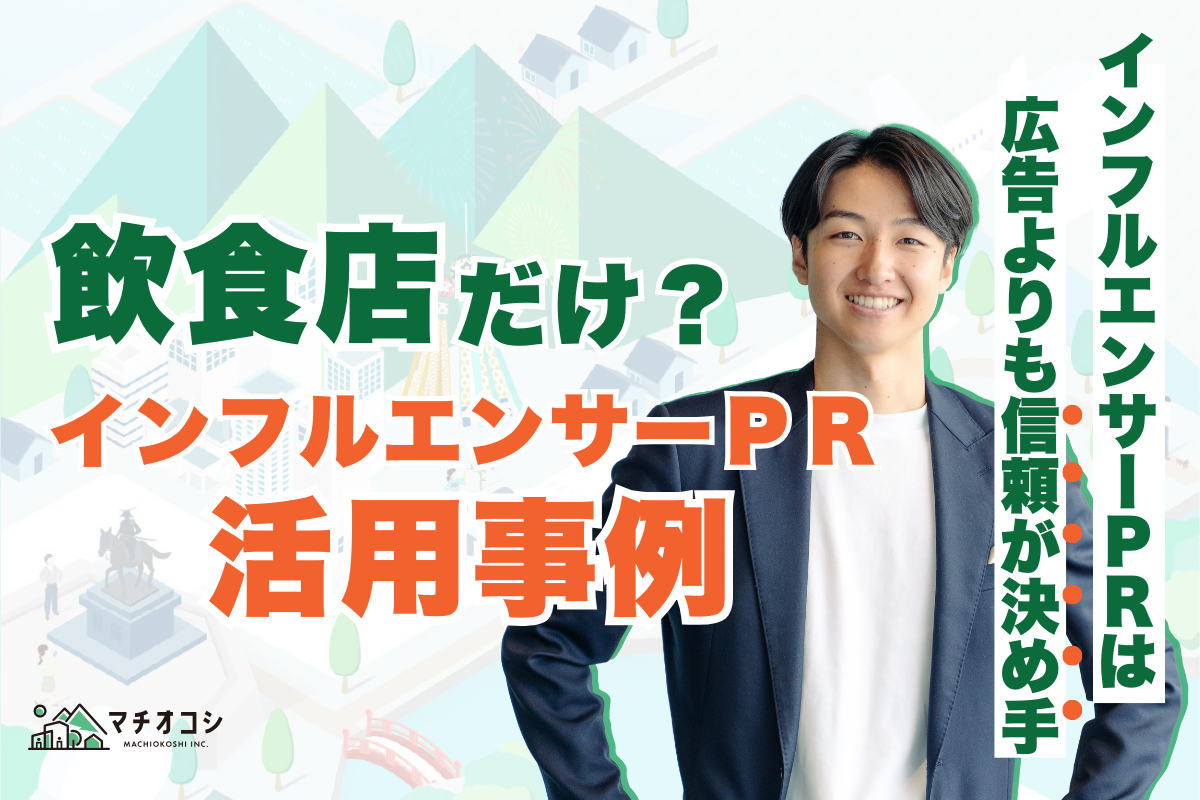「SNSは情報発信のためのツール」。そう思っていませんか?
確かにSNSは自社の情報を広める手段のひとつですが、本当に活かすべきは信頼を育てる力です。実際、SNS経由での問い合わせが直接来ていなくても、「SNSの発信を見ていて信頼できそうだと思った」と話す顧客は少なくありません。HPからの問い合わせであっても、その裏側にSNSで築かれた信頼があります。この記事では、企業がSNS運用をすべき“本当の理由”を掘り下げて解説します。
INDEX
問い合わせはHPでも決め手はSNS
多くの企業では、最終的な問い合わせや契約がホームページから行われます。
しかしその裏側には、「SNSで見ていたから」「日頃の投稿を見て信頼できると感じたから」という決め手としてのSNSの存在があります。
たとえば、SNSで日々の仕事風景やスタッフの紹介、企業の価値観を発信していると、ユーザーにとっては「どんな人が、どんな想いでやっているのか」が自然と伝わります。その積み重ねが、「この会社なら任せられそう」「一度話を聞いてみたい」といった安心感や親近感につながっていくのです。
実際に、「SNSは見ていたけれど、問い合わせはHPからした」という顧客の声は非常に多く、SNSとHPは信頼構築と最終アクションを分担する導線として機能しているといえます。
つまり、SNSはただの広報チャネルではなく、顧客の「心の準備」を整える場。企業の魅力を言葉や写真で日常的に見せることで、見込み顧客の不安を取り除き、「この会社に連絡しよう」と決断させる一押しの役割を果たしているのです。
ホームページはゴール地点、SNSはスタート地点。この2つをうまく連携させることで、より強い集客導線を築くことが可能になります。
企業がSNS運用すべき理由
企業がSNSを活用する意義は、単なる情報発信や拡散にとどまりません。SNSには、企業の今をリアルタイムに伝えながら、ユーザーとの関係性をじっくりと育てていく力があります。ここでは、企業がSNS運用をすべき「本質的な3つの理由」について、具体的に解説します。
見込み顧客との「信頼」を育てる
SNSでは、会社の雰囲気や考え方、取り組みなどが日常的に伝わります。
「まだ買うつもりはない」「すぐには依頼しない」といったユーザーに対しても、継続的に接点を持てるため、信頼感を少しずつ積み上げていくことが可能です。人は、知らない企業よりも「よく見かける企業」に親近感を覚えます。SNS運用は、その「見かける機会」をつくる重要な手段なのです。
さらに、企業が大切にしている価値観や、裏側の努力、社員の人柄が見えるような投稿を続けることで、「誠実さ」や「共感」につながる信頼が醸成されます。この、じわじわと効く信頼構築こそ、SNSの最大の武器だと言えるでしょう。
検討段階のユーザーとつながり続けられる
SNSは「今すぐ買いたい人」だけでなく、「興味はあるけれど決めきれていない人」との接点にもなります。ホームページや広告では、検討フェーズのユーザーに対して継続的な接点を持ち続けることは難しいものですが、SNSならば日々の発信を通して、自然な形で関係性を維持できます。
たとえば、ある投稿をきっかけに興味を持ったユーザーが、数週間後や数か月後に再び投稿を見て、購入や問い合わせに至るというケースは珍しくありません。このように、SNSは「検討層を育てるメディア」としても非常に有効です。
また、キャンペーン情報やお客様の声などを定期的に発信することで、ユーザーの心の中でブランドの存在感が高まり、「選ばれる理由」になるのです。
顧客の声・ニーズを拾えるリアルな場
SNSは、企業からの一方通行の発信だけではなく、ユーザーからの反応が返ってくる対話の場でもあります。
投稿に対する「いいね」やコメント、DMで寄せられる声から、顧客のリアルな感情やニーズが浮き彫りになります。たとえば、「この投稿、共感しました」「こんな商品があれば嬉しいです」などの反応は、企業にとって大きなヒントになります。それらを商品開発やサービス改善に活かすことで、よりユーザー視点に立ったビジネス展開が可能になります。
また、ネガティブな声が届いた場合も、丁寧に対応する姿勢をSNS上で示すことで、他のフォロワーからの信頼感や誠実さが伝わることもあります。SNSは、顧客と共にブランドを育てていけるリアルな共創の場なのです。
SNSは、単なる発信ツールではなく、企業の「信頼づくり」に欠かせないインフラのひとつです。 私たちは、企業の想いや価値がきちんと伝わり、ユーザーとの信頼関係を育てていけるようなSNS設計と運用をサポートしています。 「どこから始めればいいかわからない」「この運用で成果が出ているのか不安がある」そんなときは、ぜひ専門家の視点を取り入れて、貴社らしいSNSのかたちを一緒に育てていきましょう。
企業が勘違いしがちなSNS運用
SNSは手軽に始められる反面、運用に対する“誤解”が多いのも事実です。これらの思い込みが、せっかくのSNS活用の可能性を狭めてしまう原因になることも少なくありません。ここでは、企業が陥りやすいSNS運用の勘違いと、その正しい捉え方を整理します。
「バズらなければ意味がない」
SNSといえば「バズ=成功」と思われがちですが、それは大きな誤解です。確かに一時的に注目を集める投稿は拡散力がありますが、バズは偶発的なものであり、戦略ではありません。また、バズを狙うあまり話題性ばかりを追いかけると、自社のブランドイメージや信頼といった「積み上げ型の資産」が育たず、結果としてコンバージョンに結びつかないというケースも多く見られます。
SNSは「売れる」よりも「選ばれる」ための土台づくり。派手さよりも、誠実で一貫性のある発信の継続が、信頼を生み出す近道です。
「SNSは若者向けのツール」
SNS=Z世代・若年層向けという認識は、もはや時代遅れです。実際、30代〜50代のビジネス層が日常的にSNSを利用しており、BtoBの商談や採用活動のきっかけがSNSという事例も珍しくありません。また、SNSには複数の種類があり、それぞれの特色や利用者の年齢層も異なります。
ターゲットがどの年代であれ、多くの人が情報収集をしているのは事実です。SNSは「誰向けか」ではなく、「誰にどう届けるか」。年齢層で切るのではなく、行動特性で考えるべきです。
「フォロワーが増えない=失敗」
フォロワー数がわかりやすい数字であることは確かですが、それだけを成果指標にしてしまうと、SNSの本質を見誤ります。実際に「SNSを見ていたけど、フォローはしていなかった」「ずっと見ていたので安心して問い合わせた」というケースは多く、見えないファンが成果を生んでいることもあります。SNSのゴールは「見られること」ではなく、「信頼されること」です。
いいねが少なくても、投稿が誰かの記憶に残っている可能性は十分にあります。地道な積み重ねが、思いもよらぬ形で成果につながるのがSNSの特徴です。
「社内でできるから外部に頼む必要はない」
SNSは投稿するだけでなく、戦略・目的設計・社内連携・分析・改善と多くの要素が絡み合います。「とりあえず投稿係に任せておけば大丈夫」という状態では、属人化や運用疲れが起こりやすく、継続が難しくなるのが実情です。また、社内だけで運用していると客観的な視点が欠けてしまい、「何のための投稿か」が不明瞭になることもあります。
そこで有効なのが、専門家の力を借りるという選択肢です。
戦略設計やコンテンツ改善などの支援を受けることで、社内運用の精度が飛躍的に向上するケースも多くあります。リソースや体制に応じて、すべてを外注ではなく必要な部分だけ頼るという柔軟な考え方が、結果として費用対効果を高めます。
SNS運用には、見えやすい数字や一時的な反応にとらわれがちですが、企業にとって本当に大切なのは、「誰に」「どのように信頼されるか」という視点です。マチオコシ株式会社は、SNSを単なる投稿ツールではなく、信頼資産を育てる場として活用するお手伝いをしています。誤解や思い込みから抜け出し、自社らしいSNS運用を目指したい方は、ぜひ一度ご相談ください。
SNSを育てるために意識すべき運用のコツ
SNSは、ただ投稿を続ければ成果が出るというものではありません。信頼を育て、企業の価値を伝えるためには、「育てる意識」を持って丁寧に運用することが大切です。ここでは、SNS運用をより効果的に進めるために押さえておきたい3つの基本的なポイントを解説します。
目的を明確にする
SNS運用でよくある失敗が、「なんとなく始めて、なんとなく続ける」こと。その状態では、発信内容がぶれたり継続が難しくなったりして、効果が見えにくくなります。まずは、SNSを通じて何を達成したいのかを明確にしましょう。
・ブランドの認知を広げたい
・企業の価値観や文化を発信して信頼を育てたい
・採用活動につなげたい
・ファンコミュニティを形成したい
目的が定まれば、誰に向けて・何を・どのように届けるべきかが自然と整理され、投稿の内容やトーンにも一貫性が生まれます。また、運用体制やKPIの設定もスムーズになり、社内の巻き込みにもつながりやすくなります。
信頼を築けるコンテンツを発信する
SNSで成果を出している企業に共通しているのは、人間味のある発信をしていることです。商品やサービスだけでなく、その背景にある企業の想いや、働く人の声、日々の取り組みなどを丁寧に伝えることで、「この会社、なんかいいな」と感じてもらえるきっかけになります。
特に中小企業や地域密着型のビジネスでは、「企業対顧客」よりも「人対人」の関係性が重視されがちです。だからこそ、飾らない言葉や写真、社員の日常、現場のリアルな姿が、信頼を築く一歩になるのです。
どんなに小さな取り組みでも、伝え続けることに意味がある。そう考えて、日常のひとコマを大切に発信しましょう。
直接の成果だけで判断しない
SNSは、Web広告や営業活動のように「即効性のある数字」が出にくい場合があります。「フォロワーが増えない」「問い合わせに直結しない」などと感じて、運用を止めてしまう企業も少なくありません。しかし、SNSで育まれるのは、見えない信頼資産です。
「SNSを見て雰囲気が良さそうだった」「なんとなく気になっていた」という声が増えてきたら、それは確実に成果が出ている証拠です。数字だけでなく、「誰に」「どう届いているか」を丁寧に見つめながら、長期的な視点で育てる姿勢を持つことが、SNS運用成功のカギとなります。
企業のSNSは見えない信頼を育てる場所
SNS運用の効果は、すぐに「数値」として表れるものばかりではありません。
むしろ、SNSの本質的な価値は、ユーザーの心の中に少しずつ積み重なる見えない信頼にあります。SNSは、単なる情報発信の場ではありません。ユーザーとの距離を縮め、企業の姿勢や価値観を伝え、信頼を築くための“メディアです。
投稿の一つひとつが、「この企業、ちゃんとしているな」「誠実そうだな」といった印象を育て、まだ取引が始まっていない段階でも、好意の種をまくことができます。
売上やフォロワー数など、目に見える指標だけでは測れない価値が、SNSにはあります。「なんとなく見ていて、いつの間にかファンになっていた」そんな関係性を育てるのが、SNS運用の真の目的です。地道な発信が、数か月後、あるいは1年後に選ばれる理由になる。それがSNSの持つ、長期的な信頼構築力なのです。
信頼されるSNSを目指すならマチオコシ株式会社

SNSを通じて「信頼される企業」になるためには、自社の強みや想いを丁寧に言語化し、継続的に発信していくことが重要です。マチオコシ株式会社では、一社一社の「らしさ」に寄り添ったSNS運用のご提案を行っています。「社内にリソースがない」「何を発信すればいいかわからない」そんなお悩みも、お気軽にご相談ください。SNS運用を通じて、未来のお客様との信頼を育てる。その一歩を、私たちと一緒に踏み出しましょう。