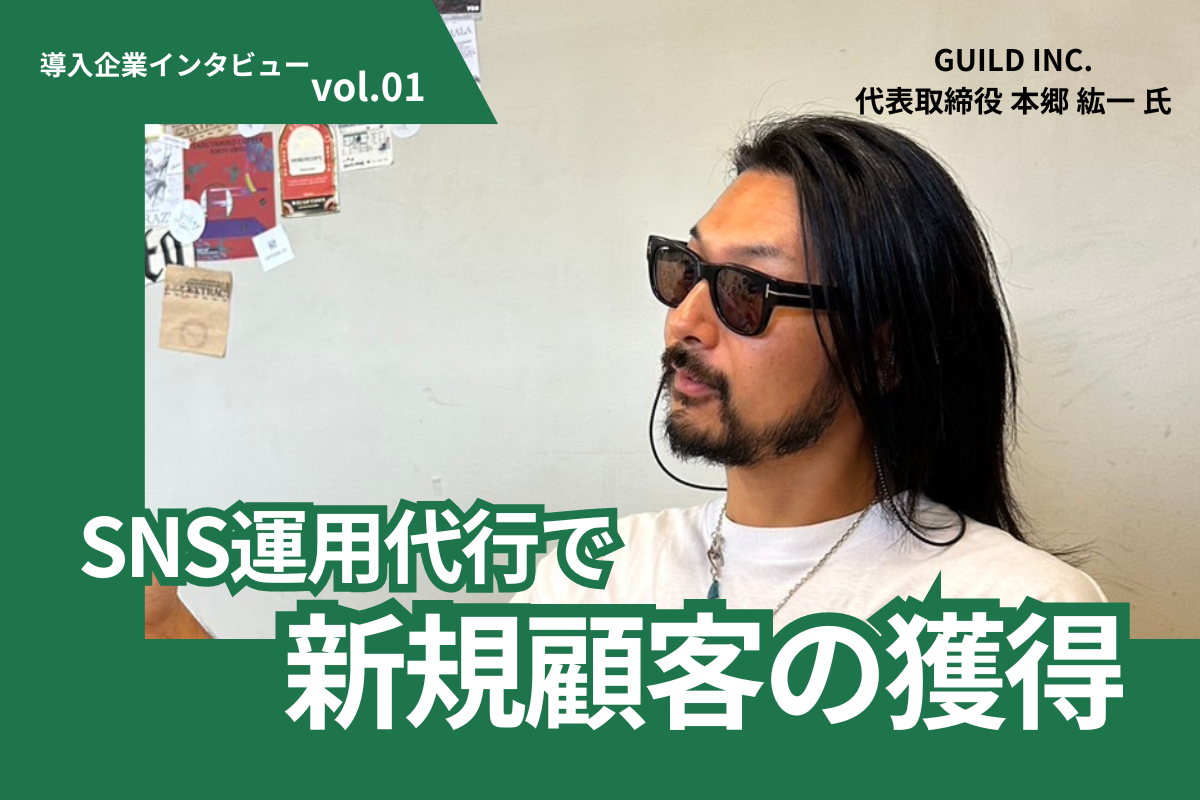企業にとってSNSは、採用・集客・ブランディングに欠かせない存在です。ユーザーとの接点を増やし、企業の魅力を可視化するための強力なツールであることは間違いないでしょう。しかし、日々の業務に追われる中で「何をどう発信すればいいのかわからない」「手間ばかりで成果が見えない」と感じてしまうのも事実です。そこで本記事では、企業のSNS運用における代表的な課題と、その“面倒”を乗り越えるための具体的な解決策をわかりやすく解説します。
INDEX
企業のSNS運用が「面倒」だと感じる理由とは?

SNS運用が続かない、あるいは始められない企業には共通した理由があります。ここからは、企業がSNS運用に対して「面倒」と感じる主な要因を見ていきましょう。
投稿内容を考えるのが負担
SNS[に「何を投稿すればいいのかわからない」という悩みは非常に多く、特に毎回のネタ出しが重荷になります。コンテンツのネタが切れると、投稿頻度が落ち、運用自体が停止してしまうケースも少なくありません。
企業らしさやブランドに合ったトーン&マナーを保ちつつ、多様な話題を選定するには、ある程度の企画力も必要です。「誰に何をどう伝えるか」を毎回考えるのは、想像以上に工数がかかります。
担当者が専門知識を持っていない
SNS運用はマーケティングの一環であり、ターゲット設計や見せ方、アルゴリズムの理解など専門性が求められます。無料ではじめられる手軽さはありますが、運用するには知識が必要です。決して、通常業務の片手間で行えるものではありません。
また、各SNSの仕様変更や流行の変化に追いつくには、継続的な情報収集も不可欠です。こうした運用スキルや戦略立案が社内に不足している場合、運用効果が頭打ちになってしまうことが多くあります。
効果が出ているのか分からない
フォロワー数や「いいね!」の数だけを追ってしまい、ビジネス上の成果にどうつながっているのかが見えづらいという課題もあります。指標の選定が曖昧だと、継続のモチベーションも低下しがちです。
SNSは「すぐに売上につながるツール」ではありません。
目的と指標を明確にしないまま運用を始めると、途中で「何のためにやっているのか分からない」と感じてしまう原因になります。たとえば、認知拡大を目的とするならインプレッションやリーチ数、採用目的なら問い合わせや応募数といったKPIを追うべきです。
継続するための体制がない
継続的な運用には、時間も人手も必要です。属人化していたり、SNS担当が他業務と兼任していたりすると、運用が途絶えてしまうリスクが高まります。
加えて、急な担当交代や退職などが発生すると、ノウハウが引き継がれずに振り出しに戻るといった事態にもなりかねません。運用のためには、社内で無理なく継続できる体制設計やマニュアル整備が不可欠です。
炎上リスクが怖い
不適切な投稿や誤解を招く表現による「炎上」も、SNS運用に二の足を踏む要因です。リスクを過度に恐れるあまり、発信自体を止めてしまう企業もあります。
一方で、リスクを正しく理解し、社内でチェックフローやガイドラインを整備すれば、炎上を未然に防ぐことは可能です。炎上しないために「何もしない」のではなく、正しく備えることが、現代のSNS運用には求められます。
ただし、この備えに対する知識が不足しているというケースは少なくありません。軽い気持ちで投稿した内容が思わぬ炎上に発展し、企業のイメージダウンにつながることは十分にあり得ます。
SNSは手軽に始められるため、運用が簡単に見られがちです。しかし、実際には戦略とノウハウが求められるマーケティングチャネルのひとつ。投稿アイデアの枯渇や体制の不安、炎上リスクへの恐怖などは、多くの企業が一度は直面する壁です。だからこそ、私たちのようなSNS運用代行会社をパートナーとして活用していただきたいのです。企画・運用の代行だけでなく、社内運用チームの育成やKPI設計、チェック体制の構築まで、ニーズに応じた支援も行っています。「投稿するだけ”のSNS」から、「成果につながるSNS」へとシフトさせたい企業様は、ぜひ一度ご相談ください。
企業のSNS運用でよくある課題とは?

運用を始めてから見えてくる課題も少なくありません。ここでは、多くの企業が直面している代表的な課題を紹介します。
投稿がマンネリ化する
最初はアイデアがあっても、運用が続くと内容が似通ってくることがあります。同じような内容が続くとフォロワーの関心も薄れ、反応が下がっていきます。
アイデアが浮かばず、他企業の投稿の真似ばかりするというのもありがちな話です。
加えて、トレンドに乗れていない、投稿タイミングが適切でないといった要因も影響します。日々の業務に追われていると、工夫や改善が後回しになりやすいのです。
社内での役割分担が曖昧
誰が原稿を書くのか、写真を撮るのか、承認は誰がするのかといった役割が不明確だと、タスクが進まず運用が止まりがちになります。
特に中小企業では、SNS業務が兼任になりやすく、業務が属人化するケースも。負担が大きく、不満が生まれることもあるでしょう。仕組み化されていないと、担当者の異動や退職が運用停止の原因になります。
数字(インサイト)を見ても活かせない
SNSにはアクセス解析やエンゲージメント率などの指標がありますが、どう読み取って改善に活かせばよいのかがわからないまま、漫然と運用しているケースは多くあります。
「数字を見て満足」ではなく、「数値を改善につなげる」ことが重要です。たとえば、投稿ごとの反応を比較し、人気のあるテーマやフォーマットを把握することで、改善のヒントが得られます。
ターゲットとズレた発信になっている
誰に向けた投稿なのかが明確でないと、見てほしい層に響かない内容になってしまいます。ターゲットを定めた発信が重要です。
「社内ウケ」を狙った投稿が増えてしまい、本来の顧客層には響かないというズレも多く見られます。ペルソナを具体的に設定し、その人に向けて話しかけるようなトーンでの発信が効果的です。
複数アカウントの管理が煩雑
事業部ごと、店舗ごとにアカウントがある場合、それぞれの運用がバラバラで統制が取れず、情報の一貫性が失われがちです。
アカウント間で発信内容に差があると、ブランドイメージの統一感が損なわれることも。共通の運用方針やテンプレート、ツール導入による一元管理で、効率化と品質向上が図れます。
SNS運用における課題の多くは、「戦略設計」と「運用フローの整備」で解決可能です。たとえば、投稿のマンネリ化には、週ごとのテーマ設計や事前にネタをプールする「編集カレンダー」の導入が有効ですし、社内での役割分担が曖昧で運用が滞る場合は、タスク管理ツールやワークフローの整備が大きな支えになります。インサイトの読み解き方やターゲット設計に関しても、社内だけで判断するのは難しいという意見は多く耳にします。弊社では、課題に応じてどの数字を見て、どう改善するかを具体的にアドバイスし、継続的なPDCAが回る体制づくりをお手伝いしています。SNS運用にお悩みを抱えている場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
面倒なSNS運用を改善するためのポイント

SNS運用の課題を乗り越えるためには、仕組みと体制を整えることが欠かせません。ここからは、実践しやすい改善策を具体的に解説します。
運用目的とKPIを明確にする
「何のためにSNSを運用するのか」「どんな成果を目指すのか」を明確にしましょう。採用、認知拡大、集客など目的に応じて、応募数、リーチ数、CVRなどのKPIを設定することで、目標に向けた改善が可能になります。
KPIが明確になれば、分析やPDCAも回しやすくなり、社内での報告・共有もスムーズになります。曖昧なまま運用することこそ、SNSが「面倒」になる原因です。
コンテンツの企画をルーティン化する
「毎週月曜は社員紹介」「水曜はサービス紹介」など、投稿の型をある程度決めておくと、ネタ切れを防げて継続しやすくなります。テンプレート化も効果的です。
あらかじめ月間スケジュールを立てておくと、担当者の負担も軽減できます。また、過去の投稿から反応のよかった企画を再活用することで、安定した運用が可能になります。
運用ガイドラインを整備する
言葉遣いや画像ルール、NG表現などをまとめた運用ガイドラインがあると、誰が投稿してもブレがなく、炎上リスクも軽減できます。
社内の確認フローやトーン&マナーを明文化することで、複数人での運用や引き継ぎ時もスムーズです。外注先と連携する際にもガイドラインがあれば意思疎通が取りやすくなります。
社内や外部の「専任担当」を置く
SNS運用は専門性のある人が一貫して見ることで効果が出やすくなります。社内では難しければ、信頼できる外部パートナーを活用するのも有効です。
専任者がいれば、投稿品質の安定だけでなく、フォロワーとのコミュニケーションや分析・改善の精度も高まります。兼任体制からの脱却は、SNS活用の質を上げる第一歩です。
SNSツール(予約投稿・分析)の活用
予約投稿ツールを使えば投稿の手間が減り、分析ツールを活用すれば改善のヒントが得られます。複数アカウントの一括管理ができるツールもおすすめです。
たとえば、投稿スケジュールを一元管理できるカレンダー型ツールや、投稿のエンゲージメント率を自動で集計してくれる解析ツールなどを活用することで、作業工数を大幅に削減できます。
SNS運用が軌道に乗るかどうかは、最初の設計で8割が決まると言っても過言ではありません。KPIの設定も、何をどこまで追えばよいかを明確にするだけで、無駄な施策に時間を割かずに済みます。
初期の段階での整備がその後の効率を左右するのです。
コンテンツ設計についても、私たちは企業ごとの事業目的やターゲットに合わせて「ネタが自動的に湧き出る企画の型」をつくるところからご支援しています。弊社のサービスは伴走型サポートです。共に成果に繋がるSNS運用を目指しましょう。
効果的なSNS運用のために外注という選択も!

SNS運用は、見た目以上に工数がかかる業務です。ネタ出しから撮影、原稿作成、投稿、分析、さらにはコメント対応やアルゴリズムへの対応まで幅広いタスクが発生します。これをすべて社内で対応しようとすると、担当者への負荷が増し、やがて「止まってしまう」原因にもなりかねません。
そこで有効なのが「SNS運用の外注」という選択です。
外注を活用すれば、企画立案から撮影、原稿作成、投稿スケジュールの管理、分析と改善提案までを一括で任せられるため、運用の質が安定しやすくなります。社内に専門知識を持つ担当者がいない場合でも、経験豊富な外注パートナーの力を借りれば、プロ品質のコンテンツを発信することが可能です。
さらに、定期的にレポートや改善提案をフィードバックしてもらうことで、自社にもノウハウが蓄積されていきます。長期的に見ても、社内リテラシーの向上や運用体制の強化につながるという大きなメリットがあると言えるでしょう。
また、反応が鈍い、何を改善すべきかわからない、という状態で悩んでいる企業にとっては、第三者の視点から運用を見直せるのも外注の強み。社内では気づけなかった課題が見えるようになり、改善スピードも大幅に加速します。
ただし、外注の質はさまざまです。単なる「投稿代行業者」ではなく、自社の目的やブランドイメージを深く理解し、共に並走してくれるパートナーを選ぶことがSNS運用の外注を成功させるカギです。事前のヒアリング力や提案力、レポートの内容なども、選定時の重要なチェックポイントになるでしょう。
- ・SNSをはじめたいが社内にノウハウがない
- ・投稿はできているが成果につながらない
- ・投稿頻度が不安定で社内工数に限界を感じている
特にこういった課題を抱えている企業には、外注という選択肢が非常に有効です。
成果につながる運用”を目指すなら自社で抱えすぎず、信頼できるパートナーの力を借りることを検討してみてください。
SNS運用に悩みがあるなら「マチオコシ株式会社」にお任せ!

SNS運用の「面倒さ」や「成果が出ない」という悩みは、どの企業にも起こりうるごく自然なものです。しかし、それを放置したままでは、せっかくのビジネスチャンスを逃してしまうことにもなりかねません。マチオコシ株式会社では、企業の課題や目的に応じたSNS活用を、企画から実行・改善まで一貫してサポートしています。「何を投稿すればいいかわからない」「社内で続けるのが難しい」「投稿しても反応がない」そんなお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。