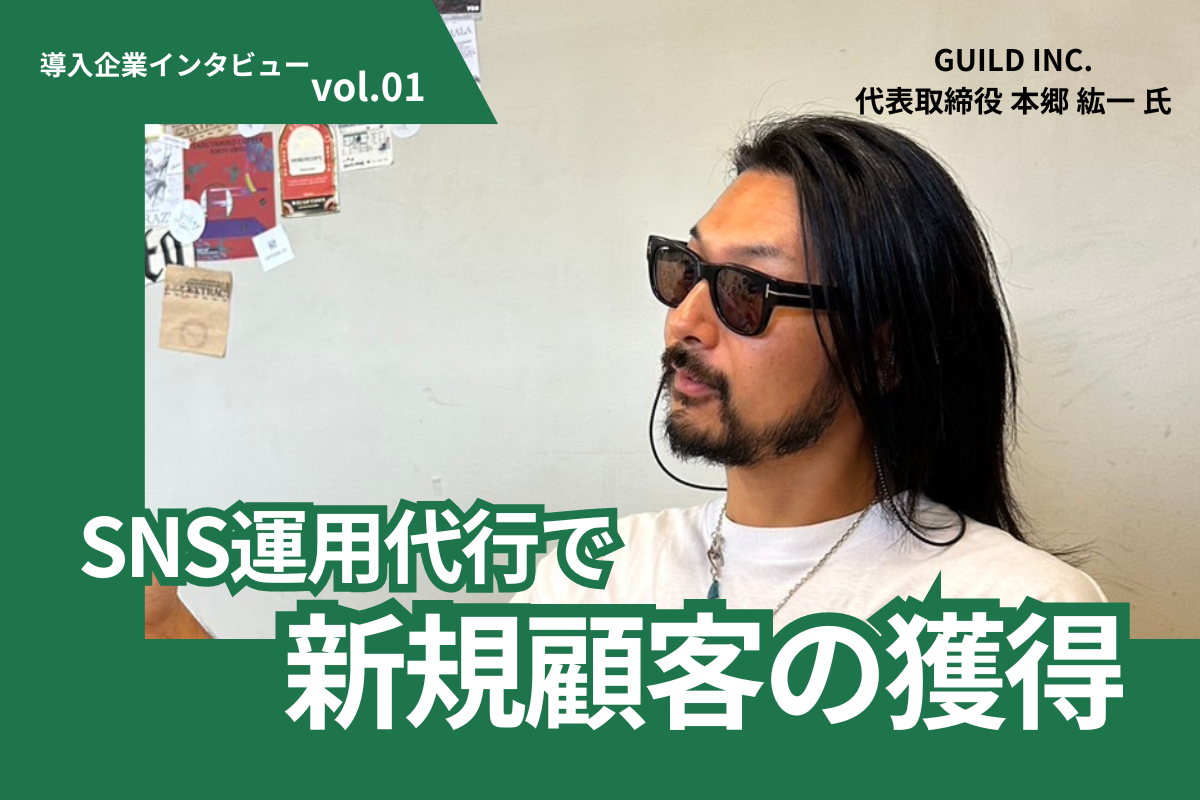SNS運用に力を入れたいと考える企業が増える一方で、「従業員が協力してくれない」「投稿ネタが集まらない」と悩む担当者も多いのではないでしょうか。企業公式アカウントだけでは限界がある中で、社員の協力を得て“中の人”の視点を取り入れた運用が注目されています。本記事では、従業員がSNS運用に協力してくれない理由と、協力を得るための仕組みや工夫を解説します。社内発信文化を根づかせるヒントとして、ぜひお役立てください。
INDEX
SNS運用における「社内協力」の重要性
SNSは単なる告知ツールではありません。企業の価値観や職場の雰囲気、リアルな日常を伝えることができる貴重なメディアです。そのためには、現場で働く社員の視点が欠かせません。
・オフィスの日常風景
・イベントや社内制度に関するリアルな声
・働く人の素顔や仕事への思い
こうした「企業のリアル」を届けるには、従業員の協力が不可欠です。社内協力が得られるとコンテンツの幅が広がるだけでなく、採用や社内エンゲージメントの強化にもつながります。
また、現場の声やリアルな日常を発信することで企業への信頼感が増せば、採用やブランディングにも大きな効果があるでしょう。単なる情報発信ではなく、従業員と一緒に伝える姿勢が、共感を呼ぶ鍵となります。
従業員がSNS運用に協力してくれない理由とは?
「協力してほしい」と声をかけても、なかなか動いてくれない 。それは単にやる気がないのではなく、「協力できない理由」が存在していることが多いものです。実は多くの社員が、SNS運用に対して漠然とした不安や抵抗を抱えており、きちんと向き合うことで解消できるケースも少なくありません。主な理由は以下の通りです。
メリットが伝わっていない
「SNSは広報やマーケティングの仕事で、自分には関係ない」と感じてしまっていると、自発的な協力は生まれにくくなります。特に、現場やバックオフィスの社員ほど「発信=会社の外の仕事」と捉えてしまいがちです。たとえば、「総務が投稿してるなら十分だろう」「現場の写真なんて誰が見るの?」といった反応が返ってくることがあります。
こうした場合は、SNS発信が採用やブランディングにどう貢献し、それが結果的に自分たちの働きやすさや評価にもつながるという流れを可視化することが大切です。
炎上への不安がある
SNSは便利な一方で、炎上のリスクを過剰に恐れてしまうケースもあります。「間違えた情報を発信してしまったらどうしよう」「社外の人に悪く捉えられたら怖い」といった不安から、発信に協力すること自体に強い抵抗を持っている人もいます。
この不安を払拭するには、社内向けのガイドラインを整備したり、発信内容を事前に確認できる体制を整えたりするなど、安心して取り組める環境づくりが効果的です。
業務との関係が見えない
「SNS投稿は本業と関係ない」と感じてしまうと、忙しい業務の中で優先順位を上げることが難しくなります。特に現場スタッフや専門職の従業員ほど、発信と自分の仕事が直結しているイメージを持ちにくい傾向があります。
「投稿によって採用が増えた」「ブランドの信頼感が上がった」といった成功事例を共有することで、自分の業務にも波及効果があると実感してもらうことが重要です。
やり方がわからない
「協力してほしい」と伝えても、具体的に何をすればよいのか分からなければ、誰も動けません。何を撮ればいいのか、どんな内容が求められているのかが明確になっていないと、戸惑ってしまいます。
投稿例やテンプレートを用意したり、「写真を撮って送るだけ」「コメントを一言もらえればOK」といった具体的な依頼をすることで、行動のハードルをぐっと下げることができます。
恥ずかしさがある
「顔を出すのが恥ずかしい」「SNSに登場するのは気が引ける」と感じる人も少なくありません。特に、SNSを普段使わない社員や内向的な性格の人にとっては、強制されることで苦手意識が強まる可能性もあります。
たとえば、ある工場では「顔が出るのは無理です」「後で同僚に何か言われるのがイヤ」として、撮影自体を断る人が続出しました。無理に出演を促すのではなく、手元の写真や風景、後ろ姿、コメントのみの協力など、複数の関わり方を用意にすることが大切です。
従業員を巻き込めないことで生じる課題
SNS運用に従業員が関わらない状態が続くと、情報の偏りや運用の形骸化、社内外への悪影響といった複数の課題が生じます。ここでは、主な5つの課題について詳しく解説します。
発信内容の質・幅が限定される
従業員が関与しないと、投稿内容が商品紹介やサービス説明など「広報目線」に偏りがちになります。現場の日常や社員の声といった「企業の温度感」が伝わらず、発信にリアリティが欠けてしまいます。
たとえば、飲食店のSNSでメニューの写真ばかりが並び、働いている人の表情や調理風景が一切見えないと、ユーザーには「人」の気配が感じられず、記憶に残りにくくなります。
担当者の負担が偏る
企画・撮影・投稿・反応のチェックまで、すべてを広報担当者や一部のスタッフに任せきりになると、リソースが不足しやすくなります。ネタ切れに悩み、投稿頻度が落ちて、やがて運用が止まってしまうケースも。
「次は何を投稿しよう」「誰も協力してくれない」と孤軍奮闘になれば、担当者のモチベーションも維持しにくくなります。
アカウントの成果が伸びにくくなる
人の存在が感じられないSNSアカウントは、ユーザーとの心理的な距離が縮まりません。企業アカウントでも、社員の声やストーリー性のある投稿があることで、共感や親しみが生まれやすくなります。
従業員が関わらないことで、いいねやシェア、フォローといった反応が伸びず、せっかくの取り組みが「効果がないもの」と見なされてしまう可能性もあります。
社内に発信文化が根付かない
発信が特定部署だけで完結していると、「SNSは自分たちには関係ない」といった空気が広がり、社内に発信文化が育ちません。むしろ「なんで広報があれを投稿したの?」というような、社内との温度差が摩擦を生むことすらあります。
逆に、現場が「これ投稿したいです」と提案してくれるようになると、企業アカウントはぐっと活性化するでしょう。発信文化があるかどうかで、SNSの継続性・拡張性は大きく変わります。
チャンスの取りこぼしが増える
たとえば、新人研修の様子、職人のこだわり、ちょっとした季節の演出などの「現場で日々生まれている出来事」は、SNS発信にとっては絶好のネタです。
従業員の協力がなければ、そうした瞬間を拾うことができず、日常の魅力が埋もれてしまいます。これは他社との差別化を図る大きな機会を逃すことにもつながりかねません。
チャンスの取りこぼしが増える
たとえば、新人研修の様子、社内イベント、職人のこだわり、ユニークな顧客対応、スタッフのちょっとした気配りや工夫など、ユーザーが共感しやすい瞬間は数多く存在します。
しかし、従業員の協力がなければ、そうした貴重なシーンをキャッチできず、結果として発信のチャンスを逃してしまいます。他社が現場発信を積極的に行っている場合は、情報発信の鮮度や信頼性で見劣りしてしまうことも。

従業員を巻き込むためにできること
SNS運用に対する従業員の協力を得るためには、「やってほしい」と頼むだけでは不十分。安心して関われる環境を整え、SNS運用の目的や意味を理解してもらうことが不可欠です。以下のような工夫を通じて、従業員を自然に巻き込む仕組みをつくりましょう。
SNS運用の目的を社内で共有する
「採用強化のため」「企業文化の発信のため」など、運用の目的を明確に伝えることは大前提です。ミッションやビジョンと紐づけて共有することで、従業員が自分ごと化しやすくなります。目的が伝わることで、「なぜやるのか」が腹落ちし、行動への抵抗も和らぎます。
安心して参加できる仕組みをつくる
SNSに対する不安を払拭し、従業員が「自分にもできそう」と思える環境を整えることは、巻き込みの第一歩です。スマホで気軽に写真を撮って共有できるチャットグループやフォルダを用意するなど、「気づいたら投稿」ではなく「気づいたら素材提供」できる仕組みにするのもよいでしょう。 大切なのは、「やりたいけど不安」な人が一歩踏み出せる環境を、企業側が先回りして整えておくことです。
社内向けガイドラインの作成
投稿内容の範囲や禁止事項、写真やコメントの扱いなどを定めたガイドラインを共有することで、社員は「何をしていいか/いけないか」が明確になり、不安が軽減されます。併せて、投稿の事例集やフォーマットを用意すると、初めてでも動きやすくなります。
誰が何をすればよいかを明確にする
「自由にやっていいよ」ではなく、「この枠内で、これをしてくれると助かる」という具体的な依頼の仕方がポイントです。たとえば「現場の写真を週に1回LINEで送ってください」「今月の投稿テーマは○○なので、一言コメントをお願いします」など、タスクを細かく分けて伝えると行動につながりやすくなります。
SNSに関する小さな成功体験を共有する
社員が「反応があった」「お客様から見たよと言われた」といったポジティブな体験を共有すると、社内に好循環が生まれます。社員が登場した投稿が特に反響を得た例、SNSを通じて採用につながった例、投稿が社外との新しい接点になった例などを、定例会議などで紹介しましょう。成果を見える化することが、次の協力者を生むきっかけになります。
社内アンバサダー制度・表彰制度の導入
SNS投稿やネタ提供に貢献した社員を表彰したり、任意で「社内アンバサダー」として任命したりするのも効果的です。SNSが得意な社員に一部業務を委ねることで、巻き込みやすくなるだけでなく、社内に発信の文化が根づいていきます。感謝や称賛をしっかり伝えることも、モチベーション維持につながります。
従業員を巻き込んだSNS運用を実現するには、「協力してもらう」ではなく「一緒につくる」というスタンスが欠かせません。どんなに仕組みを整えても、命令や指示だけでは人は動きません。重要なのは、従業員一人ひとりが「自分たちの言葉で会社を伝えている」という実感を持てる環境をつくることです。そのためにも、目的の共有、安心できるルールの整備、貢献へのフィードバック、成功体験の可視化といった積み重ねが必要です。SNS運用は、単なる広報活動ではなく、社内外のつながりを育てる文化づくりの一環。だからこそ、協力ではなく「共創」という意識を持つことが何より大切です。
それでも難しいと感じたら、プロと連携する選択肢も
どうしても社内リソースでの運用が難しい場合は、SNS運用代行や伴走支援サービスを活用するのも一手です。
たとえば、プロと連携することで以下のような支援が可能になります。
・発信の目的やトーンを整理して、運用方針を明確化
・投稿テーマやネタの企画立案
・投稿文や画像の作成代行
・社内向け運用ガイドラインの整備
・社員インタビューや現場取材の実施
・成果レポートや運用改善の提案
・SNS運用に関する社内向けセミナーや勉強会の開催
・炎上リスク対策やチェック体制の構築支援
従業員の声をコンテンツ化するサポートも受けられるので、自社の魅力を自然な形で発信することができます。外部の視点を入れることで、SNS運用への社内理解が深まり、結果として「社内が動き出す」きっかけになるケースも少なくありません。
従業員がSNS運用に協力してくれない背景には、目的が伝わっていない、不安がある、やり方がわからないといった“協力できない理由”が隠れていることが多くあります。そのため、いきなり「協力して」とお願いするのではなく、社内でSNS運用の目的や意義、具体的な関わり方を共有する場を設けることが非常に重要です。特に効果的なのが、事前の社内向けセミナーや説明会です。SNS運用が自分たちにとってどう関係するのかを“自分ごと化”してもらうことができます。まずは社内の理解と共感を得るところから。小さな一歩が、協力体制と発信力のある企業文化をつくる土台になります。
従業員がSNS運用に協力してくれないことでお悩みなら「マチオコシ株式会社」

従業員がSNS運用に協力してくれないという声を耳にすることは、非常に多くあります。そのような場合に有効なのが、「事前セミナー」の開催です。なぜ企業にSNS運用が必要なのか、どのような効果があるのかを理解してもらい、「業務の一環」として捉えてもらうことが何よりも重要です。実際、弊社の事前セミナーを受けていただいた後には、「従業員の姿勢が変わった」「嫌がっていたのに楽しむようになった」という嬉しいお声をいただいております。従業員がSNS運用に協力してくれないことにお悩みの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。