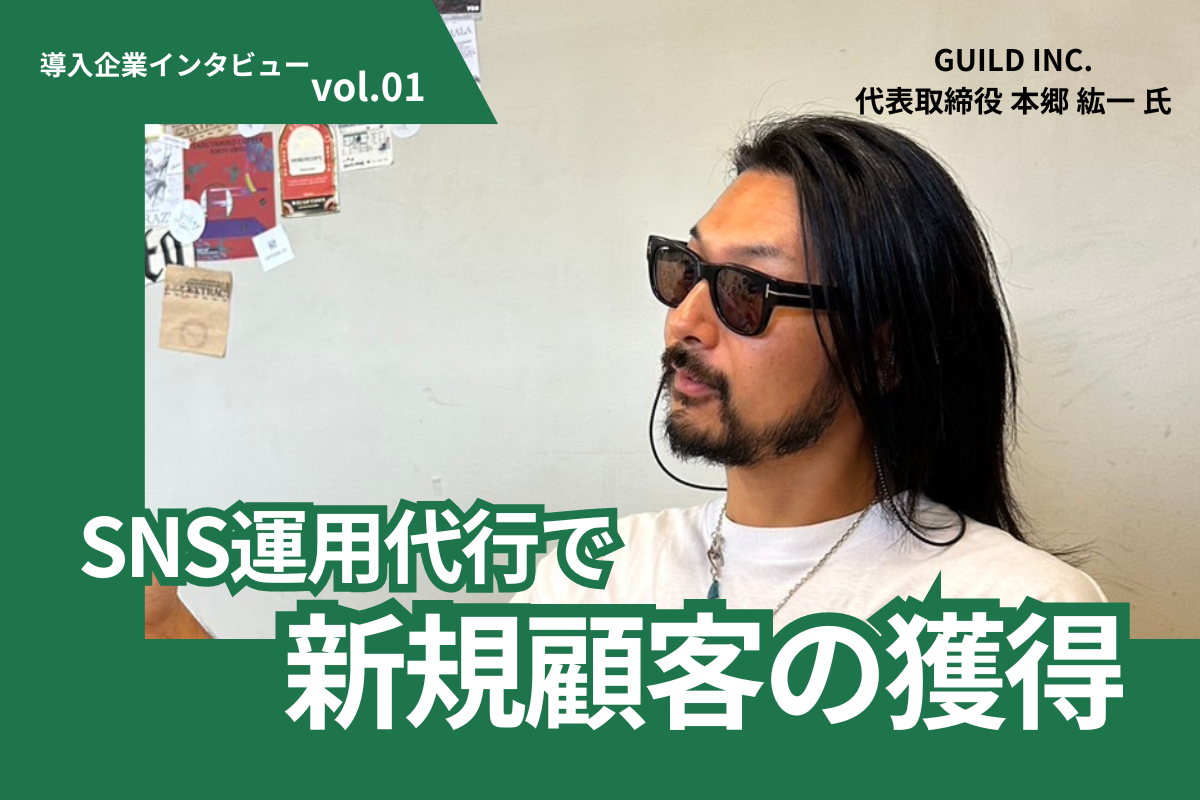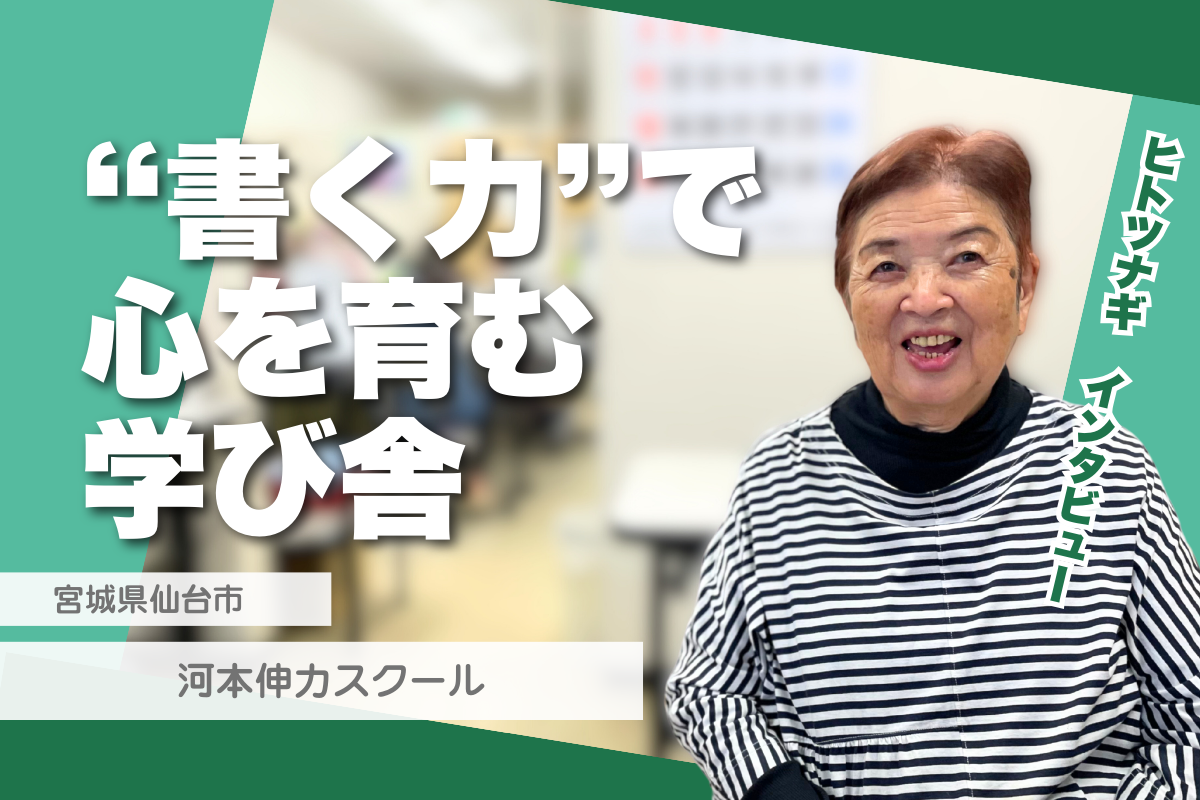企業や店舗のSNS運用において、「スタッフがSNSに出たがらない」「顔出しNGが多くてコンテンツが作れない」といった悩みを抱える担当者は少なくありません。しかし、現場スタッフの協力が得られなければ、リアルな情報発信や親しみのある投稿は難しくなります。この記事では、スタッフがSNSに非協力的な理由を整理したうえで、協力を得るための具体的な工夫とアプローチ方法をご紹介します。
INDEX
スタッフがSNSに協力してくれない理由

まずは、なぜスタッフがSNSに協力的でないのか、その背景を理解することが重要です。理由を知ることで、適切な対応やコミュニケーション方法を見つけやすくなります。表面的には「恥ずかしいから」「忙しいから」と言われても、そこにはもっと深い理由や不安が隠れていることがあります。
顔出しやプライバシーの懸念がある
スタッフの中には、「顔がインターネットに残るのが嫌だ」「家族に見られたくない」「勝手に知らない人に見られるのが怖い」といったプライバシー面での不安を持つ人が少なくありません。
特にSNSは検索や拡散の影響が大きく、一度投稿された写真や動画は、完全に削除することが難しいという特性もあります。
また、「前職の関係者に見られたら困る」「子どもや家族に迷惑がかかるのでは」といった心配もあり、顔出しを拒否するのは決して消極的な姿勢ではなく、自衛的な行動とも言えます。このような不安を理解せずに「出てよ」と一方的に依頼してしまうと、信頼関係の溝が深まってしまう恐れがあります。
SNSの目的や効果が理解されていない
スタッフがSNS運用に協力的でないもう一つの大きな要因は、「何のためにやっているのか」が見えていないことです。たとえば、「投稿したところで売上に繋がるの?」「ただの自己満では?」といった疑念があるままでは、協力しようという気持ちは芽生えません。
企業や店舗にとってはマーケティングの一環であっても、現場のスタッフにとっては「業務外のよくわからない作業」にしか見えないことも。そのギャップを埋めるためには、「SNSの目的」「スタッフが関わることの意味」「成果につながるプロセス」を、具体的な事例や数字を交えて共有することが欠かせません。
やらされ感が強く、モチベーションが湧かない
「○○さん、今日の投稿で顔出しお願いね」と、事前の説明や同意もなく依頼されれば、誰でも戸惑います。協力というよりも「命令」のように聞こえてしまえば、反発やストレスの原因にもなりかねません。
特に、「SNS運用=広報担当の仕事」という意識が社内で定着していない場合、現場スタッフにとっては「急に巻き込まれた」と感じやすくなります。やらされ感が強いと、自発的なアイデアや工夫も生まれづらく、結果として機械的な投稿や非協力的な雰囲気につながります。
この背景には、「日常業務に余裕がない」「成果が見えづらい」「無理強いされているように感じる」など、心理的な負担が潜んでいるケースも多いため、丁寧な対話や配慮が必要です。
社内文化としてSNSを根付かせるには?

一時的な盛り上がりや個人任せの運用では、SNSの効果は持続しません。SNSを「当たり前の活動」として定着させるには、社内全体の理解と、組織としての仕組みづくりが欠かせません。ここからは、SNS運用を社内文化として根づかせるために意識したい3つのポイントをご紹介します。
トップやリーダーが率先して関わる
SNS運用を社内文化として根付かせるには、まず「上層部がどう関わるか」が大きなカギになります。経営者やマネージャーといったリーダーが自ら出演したり、投稿に登場したりすることで、スタッフの心理的なハードルを大きく下げることができます。
また、トップがSNS運用に関心を持ち、「発信は重要な仕事だ」と公言することで、社内全体の意識も変わってきます。現場任せではなく、上層部が一緒に当事者になることで、SNS運用が会社としての取り組みであるという認識が広がります。
SNS=仕事の一部として浸透させる
SNS運用を「特別な作業」や「手が空いたときにやるもの」として扱っている限り、安定的な運用や協力体制の構築は難しくなります。SNSを仕事の一部として捉え、スケジュールやタスクの中に組み込む工夫が求められます。
たとえば、以下のような仕組みが有効です。
・週1回のSNSミーティングを実施する
・投稿計画を月次スケジュールに組み込む
・撮影や素材収集のための時間をあらかじめ確保しておく
また、「SNS担当者」だけが担うのではなく、各部署や店舗からサポート係を選出するなど、運用チームを社内に構築することも効果的です。
社内にSNS文化を根づかせるには、「業務」として認識される仕組みづくりと、関わる人すべての納得感が欠かせません。誰かひとりに任せるのではなく、組織全体で「育てていく」意識があってこそ、SNSは強い企業資産になります。
私たちは、SNS運用を単なる代行で終わらせるのではなく、社内に定着する運用体制の構築までを伴走支援しています。トップの理解を得る工夫、スタッフを巻き込むための設計、評価制度との連携まで。SNSが“一過性のブーム”で終わらないよう、仕組みとして組み込むお手伝いが可能です。
SNS運用【前】にできるスタッフへのアプローチ方法

SNS運用をスタートする前段階での丁寧な準備やコミュニケーションは、スタッフの理解と協力を得るカギになります。このフェーズで信頼関係を築くことができれば、スムーズな巻き込みや、継続的な関与にもつながります。「いきなり出演を依頼する」のではなく、事前の土壌づくりが成果を左右するといっても過言ではありません。ここでは、運用開始前に意識したいアプローチのポイントをご紹介します。
運用目的と役割を明確に伝える
「なんとなく始めたSNS」では、誰も本気で関わろうとはしません。まずは、SNS運用の目的や背景、目指すゴールを社内で丁寧に共有しましょう。
たとえば、こんな目的が考えられます。
・「お店のファンを増やしたい」(認知拡大・集客)
・「採用活動にSNSを活かしたい」(会社の雰囲気の可視化)
・「ブランドイメージを強化したい」(世界観や価値観の発信)
こうした企業としての目的明確に伝えることが第一歩です。また、スタッフに対しては次のように本人に紐づけた役割の説明が効果的です。
・「○○さんの笑顔や丁寧な接客が、企業の信頼感を伝える一番の要素です」
・「普段通りの姿を見せることが、応募者の安心感につながります」
必要に応じて、簡単な資料などで視覚的に伝えると、より納得感が高まるでしょう。
強制ではなく選択肢として提示する
全員に同じ協力を求めるのは現実的ではありません。「出演=協力」という固定観念を取り払い、できる範囲で関われる選択肢を複数提示することが大切です。
たとえば、以下のような「役割の幅」を用意しておきましょう。
・顔出しで出演(動画や写真に登場)
・写真のみ参加(後ろ姿や手元など)
・コメント/紹介文の提供(ナレーション協力)
・撮影補助/小道具準備(裏方でのサポート)
・投稿文の確認/校正(文章が得意な人向け)
・SNSのネタ提供(投稿のアイデア出し
このように「関わり方を選べる」状態にしておくことで、スタッフがやらされてい”感覚から解放され、自分の意思で参加しやすくなります。
SNSの基本ルールとガイドラインを共有する
スタッフがSNS協力に不安を感じる理由のひとつに、「どこまでやって大丈夫なのか分からない」という情報不足があります。だからこそ、あらかじめガイドラインやQ&A集を用意して共有しておくことが効果的です。
たとえば、以下のような項目を事前に伝えておくと安心です。
・SNS投稿前のチェックリスト: 内容確認、本人承諾、社外秘の情報はないか
・NG投稿の具体例:誹謗中傷、個人情報、取引先の情報、ネガティブ表現
・削除/修正対応ルール:間違えた場合にどう修正するのか、誰が対応するのか
・困ったときの相談窓口:SNS担当者名と連絡先、緊急時の対応フロー
さらに、「顔出しの前には必ず確認をとる」「発言は自由だが編集確認あり」など、ルールが曖昧になりやすい部分こそ、丁寧に明文化することが重要です。スタッフが「守られている」「リスクは最小限にできる」と感じられる環境があれば、自然と参加しやすくなります。
SNS運用【中・後】にできるスタッフへのアプローチ方法

SNS運用は「始めること」よりも、「続けること」のほうが難しいと言われます。一度は協力してくれたスタッフも、モチベーションが続かなかったり、忙しさから徐々に離れていってしまうことはよくある話です。継続的な運用を実現するためには、運用の中盤以降こそ、社内との関係性の見直しやアプローチの工夫が必要不可欠です。ここでは、運用が軌道に乗った後にこそ実践したい「巻き込み続けるための工夫」をご紹介します。
投稿の反響を定期的にフィードバックする
SNSに協力しても、その結果が見えなければ「やった意味があるのか分からない」と感じてしまいます。だからこそ、投稿の反応や反響を定期的かつ具体的にスタッフへフィードバックすることが重要です。
以下のような声掛けも有効でしょう。
・「先週の投稿、再生数が1,200回を超えました」
・「○○さんに会いたいというコメントが届いています」
・「新規来店のお客様がInstagramを見て来たとおっしゃっていました」
このように数値やエピソードを交えて伝えると、スタッフ自身が「自分の行動が誰かに届いた」と実感でき、自然と次の協力意欲につながります。社内掲示板に貼ったり、月1回の朝礼で紹介したりと、見える形で共有することも効果的です。
SNS協力を評価や感謝にしっかり反映する
人は「貢献が認められている」と感じたとき、最もやる気が高まります。SNSへの協力も例外ではありません。一言のお礼やちょっとした称賛が、継続的な参加の大きなモチベーションになります。
加えて、社内の評価制度に以下のようなSNS協力を正式に組み込むのもおすすめです。
・表彰やインセンティブ
・月間MVP
・手当制度
これらを導入すれば、SNS活動が単なるおまけの業務ではなく企業活動の一部として位置づけられるようになります。
小さな協力からでも巻き込んでいく
最初から「出演してほしい」「主役になって」と頼まれると、多くのスタッフは身構えてしまいます。そこで効果的なのが、「小さな協力から始める」というアプローチです。
前向きになれないスタッフに対しては、以下のような役割から与えてみるのも良いでしょう。
・商品を並べるだけ
・撮影の背景に映るだけ(後ろ姿OK)
・コメントを一言書くだけ
・撮影のアシスタントとして参加するだけ
このように、協力のハードルを極限まで下げることで、「これくらいならできるかも」という安心感が生まれます。そして一度関わった人ほど、「次もやってみようかな」という気持ちが芽生えやすくなるのです。
SNS運用代行会社とタッグを組む
運用が続かない理由のひとつに、人手やノウハウの不足があります。「投稿を継続するのがしんどい」「ネタが尽きてきた」「社内での巻き込み方が分からない」といった課題が積み重なると、SNSは停滞しがちです。スタッフの協力を得ることは、さらに困難になるでしょう。
そんなときこそ、信頼できるSNS運用代行会社とタッグを組むことが有効です。SNS運用代行会社は、具体的に以下のような支援をしてくれます。
・投稿作成/企画の代行
・運用レポートの作成と成果分析
・社内向けのSNSマニュアル整備
・社員向けセミナーや説明会の実施
・社員を巻き込むための施策立案
単なる投稿代行にとどまらず、「企業全体でSNSに取り組む体制づくり」までサポートしてくれる会社を選ぶと、社内の温度感が一気に変わります。外部の力を借りることは、弱さではなく戦略です。
スタッフの協力を得られないことにお悩みなら「マチオコシ株式会社」

「SNSに出てくれる人がいない」「何度説明しても協力が得られない」とお困りの企業様へ。マチオコシ株式会社では、企業のSNS運用前に「事前セミナー」を開催し、社内全体にSNSの必要性を十分に理解していただく時間を設けております。スタッフの協力を「強制」ではなく「文化」に変えていくことで、効果的なSNS運用が叶います。社内にSNSを自然に根づかせ、誰もが“ちょっと楽しんで協力できる”体制を一緒につくりませんか?