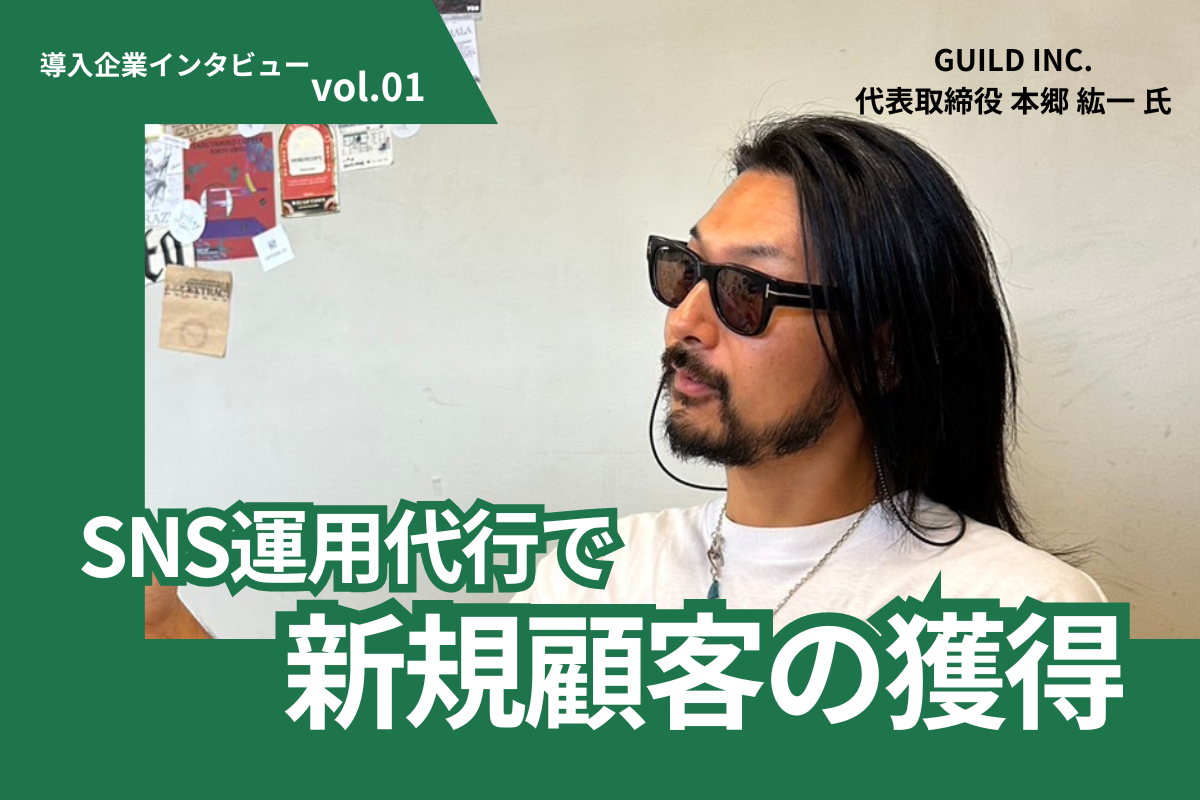「SNSで発信しても、なかなか伸びない」「フォロワーが増えないのは地域だから?」
そんな悩みを抱える地方企業は少なくありません。確かに、都市部と同じやり方では、地域ならではの魅力や課題にマッチしないことも。本記事では、地方企業だからこそ活かせるSNSの伸ばし方や、押さえておきたいポイントを解説します。
都市部と同じ戦略では伸びにくい理由
地方企業がSNS運用を始めるとき、多くの場合「都市部で成果を出しているやり方」を参考にしがちです。しかし、地方と都市部では、人口規模・競合環境・人とのつながり方など、前提条件が大きく異なります。そのため、都市部と同じようなSNS戦略を採っても、思ったような成果が出ないことも少なくありません。ここでは、なぜ都市部の戦略をそのまま当てはめるのが難しいのかを、3つの視点から解説します。
市場規模や競合状況が異なる
都市部では膨大な人口と情報量の中で、多種多様な企業がSNSを活用しており、トレンドの移り変わりも非常に速いのが特徴です。バズを狙った投稿や、有名インフルエンサーとのタイアップなど、大規模かつスピード感ある施策が主流です。
一方で、地方は人口も情報量も限られており、認知拡大のスピードはどうしても緩やかになります。
だからこそ、地方では「広く届ける」より「深く届ける」戦略が有効です。市場規模が小さい分、万人受けを狙うのではなく、地元住民や特定の関心層に刺さるコンテンツ設計が求められます。
たとえば、観光地であれば「地元の人しか知らない○○」のようなディープな情報や、農産物を扱う企業であれば「○月限定の採れたて○○」といった季節性を活かすなど、地域ならではのニッチな価値を打ち出すことで差別化できます。
「話題性」よりも「信頼性」が求められる
地方では、SNS上での発信内容だけでなく、「誰が言っているのか」が強く意識される傾向があります。これは、地域内の人間関係が密接であることが影響しているのでしょう。匿名性が高い都市部と違い、「あの○○さんが言っているなら間違いない」というように、発信者の顔や実績、日頃の姿勢がコンテンツの信頼性に直結します。
そのため、フォロワー数よりも、日々のやりとりや地道な情報発信が重視されます。
たとえば、商品の魅力を語るだけでなく、「○○町の○○さんに使ってもらった感想」といったリアルな声を取り上げることで、より共感と安心感を得られるでしょう。
オフラインとの接点が密接
都市部ではオンライン完結型の購買行動が一般化しているのに対し、地方ではSNSと実際の店舗・人とのつながりが深く関連しています。たとえば、地域の直売所やカフェ、イベントなどに実際に訪れた人が、体験をSNSで発信するという流れが日常的に起きます。
このように、リアルな体験がSNSの投稿や口コミにつながる構造があるため、オフラインの取り組みとSNSを連動させる仕掛けが重要です。たとえば、イベントでのハッシュタグキャンペーンや、来店特典としてSNSフォローを促す仕組みなど、SNSをリアルの延長線として活用することがポイントです。
また、店舗スタッフや地域住民との写真投稿、手書きPOPや季節の飾り付けをSNSで紹介するといった「人の温度が伝わる投稿」は、都市部以上にエンゲージメントを生み出しやすい傾向にあります。
地方企業がSNSを伸ばすためのポイント
都市部とは異なる土壌でSNSを伸ばしていくには、地域特性に合った発信スタイルが必要です。人口規模や関係性の濃さ、情報の届き方など、地方ならではの強みを活かせば、小さなアカウントでも着実にファンを増やすことができます。ここでは、地方企業が共感と信頼を集めながら、SNSの成果を伸ばしていくための実践ポイントを紹介します。
地元密着型のコンテンツを発信する
地域の空気感や生活感が伝わる投稿は、地元の人の共感を呼びやすく、エンゲージメントにつながりやすい傾向があります。たとえば、地元の四季折々の風景、地域のグルメ、昔ながらの風習、新店舗のオープン、桜の開花、雪景色などの町の小さな変化は、見慣れた日常だからこそ心に残りやすいのです。
地元のお祭りや学校行事の様子、商店街の裏側など「地域に住む人の誇り」を刺激するような内容は、フォロワーが「うちの町のことが紹介されてる!」と感じやすく、自然と投稿の拡散や保存につながります。
また、地元の方言をあえて使った投稿や、子どもの声、地元BGMなども親近感を生む要素になります。地域外の人にとっては旅先気分で新鮮に映り、地域内の人にとっては懐かしさを感じたり喜びを感じたりする情報源になる。そんな視点が大切です。
「誰が発信しているか」がわかる顔出し・人柄重視の投稿
都市部のようにブランドや商品そのものの知名度に頼ることが難しい地方では、「この人がやっているお店なら安心」「この人の想いに共感できる」といった人ベースの信頼構築が非常に重要です。
顔写真を載せるだけでなく、以下のような投稿が効果的です。
・店主や社員の日常を紹介
・接客の裏話や常連さんとのエピソード
・趣味や地元愛がにじむ個人的な発信
特に小規模な店舗や個人経営のビジネスでは、「この人に会いたいからお店に行く」「この人を応援したいから買う」といったファンベースの動きが起こりやすくなります。信頼関係を築くためには、きれいすぎる写真や売り込み色の強い投稿よりも、等身大で誠実な人柄が伝わる投稿を意識しましょう。
ハッシュタグは「地域+業種」で差別化
SNS上での発見されやすさを高めるには、ハッシュタグの工夫がカギになります。
過去には大量のハッシュタグを使用することがありましたが、現在は ハッシュタグを絞って活用するのが主流 です。検索されやすい言葉に厳選することで、より効果的にユーザーの目に留まります。
特に 投稿内容と関係のないハッシュタグ をつけてしまうと、アリゴリズムの影響でリーチ数が伸びにくくなるため、注意が必要です。また、オリジナルのタグは乱用せず、必要なときだけに 限定しましょう。検索経由での流入を狙うには、「地域名+業種・ニーズ」 を掛け合わせたハッシュタグが有効です。
【ハッシュタグの例(〇〇=地名)】
#〇〇カフェ(〇〇=地名)
#〇〇美容室
#〇〇テイクアウト
#〇〇子連れ
#〇〇食材ランチ
これらは地元ユーザーが検索に使いやすいキーワードなので、自然な流入が期待できます。
地元メディアやインフルエンサーとの連携
地方には、大手メディアにはない密着力と信頼感をもった情報源があります。地元のフリーペーパー、タウン誌、ケーブルテレビ、ローカルFMラジオ、地域インフルエンサーなどは、特定地域での発信力・波及力が高く、SNSとの連携によって相乗効果を発揮します。
具体的には、以下のような方法が有効です。
・新商品を地元情報誌のSNSアカウントで紹介してもらう
・地元YouTuberにお店を紹介してもらう
・ラジオで出演し、放送後に放送内容をSNSで再共有する
・地域イベントでコラボ企画を実施し、投稿をお互いにタグ付けする
「地域で見たことがある人・聞いたことがある名前」に触れることで、投稿の信頼性が一気に上がります。外部メディアとのつながりを意識的に作り、オンラインだけでなく「まちぐるみの発信」を仕掛けていくのが、地方SNS戦略の強みです。
SNS運用のゴールは「バズる」ことではありません。重要なのは、地元に根ざし、関係を育て、長く愛される存在になること。そのためには、日々の小さな発信の積み重ねが何よりも大切です。
地方だからこそできるSNS戦略とは?
都市部では見過ごされがちな小さな魅力も、地方では確かな個性として際立ちます。人口が少なく、つながりが濃い地域社会では、SNSは単なる情報発信の手段ではなく、人と人との信頼を育てる場です。リアルとの距離が近いからこそ、「地域で愛されるブランド」はSNSによって着実に育っていきます。地元との関係性を深めながらファンを広げるには、都市部とは異なる視点と工夫が必要です。ここでは、地方ならではの環境を活かしたSNS戦略の実践例を紹介します。
コミュニティ重視の丁寧なリプライ対応
SNS運用において、フォロワーとのコミュニケーションは非常に重要です。
特に地方では、実際に顔を合わせたことがある、共通の知人がいるといった人のつながりが前提となるケースも多く、返信対応ひとつで信頼度が大きく変わります。コメントやDMに対して真摯に向き合う姿勢は、「このお店(会社)はちゃんと見てくれている」という安心感につながります。誠実な対応が信頼に直結するのが、地方ならではのSNSの特長です。
やりとりを通じて応援したくなる存在としての関係が深まれば、投稿の反応だけでなく実際の来店・利用にもつながります。
常連客・ファンを巻き込んだ投稿企画
地方企業にとって、常連客や地元住民はただの顧客ではなく、心強い協力者でもあります。こうした人々を巻き込んだ投稿企画は、双方向の関係を築くだけでなく、自然なかたちでSNS上での認知拡大を促してくれます。
たとえば、常連客の一言から始まったメニューを紹介したり、地元の子どもが描いたイラストを投稿に使用したりすることで、「自分たちの町のお店」「あの人が関わっている」といった身近さが生まれます。投稿に登場した知人を通じて話題が広がることも多く、拡散のきっかけにもなります。何より、人と人との関係性が可視化された投稿は、他の誰かにも好感を持たれやすいのです。
地域課題と向き合うストーリー発信
地方には、過疎化や高齢化、空き家問題、産業の衰退など、地域ごとの課題が数多く存在します。そうした現実から目をそらさず、企業や店舗としてどのように地域と関わり、何を目指しているのかを丁寧に発信することは、多くの共感を呼びます。
たとえば、後継者不足の中で地元の伝統を継承している話や、子育てと両立しながら働くスタッフの声、地元食材にこだわる理由などは、企業の価値観や使命感が伝わるストーリーになります。SNSでバズを狙う投稿ではなくても、「応援したくなる」「信頼できる」といった印象を残すことができ、ファンとの関係性をより強くする効果があります。
近隣企業とのコラボ投稿
地方では、同じ地域内の事業者同士が連携しやすいという利点があります。ライバルとして競い合うのではなく、地域全体を盛り上げる仲間としてつながりをつくることで、SNS運用にも相乗効果が生まれるでしょう。
たとえば、近所のパン屋とコーヒー店が一緒に紹介投稿を作ったり、商店街内の複数の店舗がテーマを決めて投稿を統一したりすることで、フォロワーがそれぞれのアカウントに自然と流れ、認知が広がっていきます。地域の事業者同士が顔を合わせる機会がある地方だからこそ、連携のハードルは低く、温かみのある発信が生まれやすいのも特長です。
このように、地方には都市部にはないSNS戦略の余地があります。規模は小さくても、人との関係を軸にした発信を積み重ねていくことで、強くてあたたかいブランドが育っていきます。地方だからこそ実現できるSNS活用を、ぜひ自社でも取り入れてみてください。
地方企業ならではの活きたSNS運用なら「マチオコシ株式会社」

地方のSNS運用には、地方企業だからこその楽しみ方や面白さがあります。都市部と同じ運用ではなく、地方だからできる運用をすることが成功のカギです。私たち「マチオコシ株式会社」は、まだ広く知られていない地方の素晴らしいサービスや商品の魅力を最大限に引き出し、適切なマーケティングを通じて、地域の価値を全国に発信することを得意としております。
「地域の強み」「人とのつながり」を活かすSNS運用へ。地方企業だからこそできる発信で、一緒に御社のファンと未来をつくっていきましょう。